 キャリア採用
キャリア採用
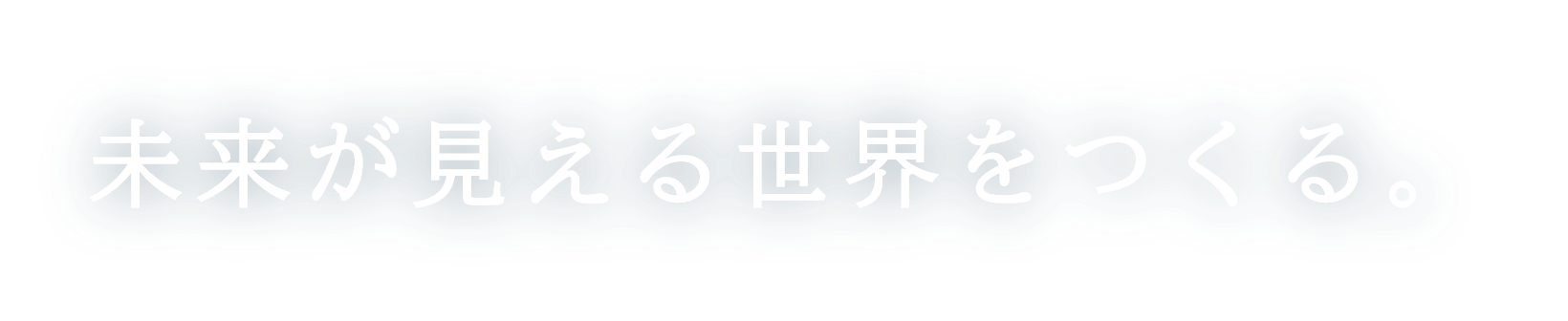
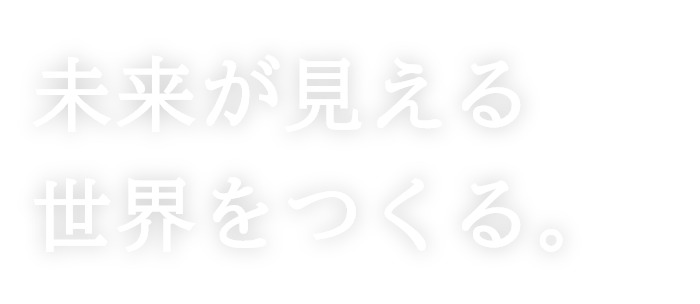
マイナビは、働く、学ぶ、さまざまな「わたし」の人生をサポートしています。就職、転職、バイト、人材紹介などのHR領域からマイナビニュースなどのメディア領域まで、幅広いマイナビの事業とサービスについてご紹介いたします。


マイナビの幅広いビジネスはセールス、クリエイティブ、マーケティング、エンジニアやコーポレートなど、さまざまな職種の協働により支えられ成長を続けています。
福利厚生や会社の各種制度など、マイナビでの働く環境についてお伝えします。

マイナビのさまざまなビジネスフィールドや仕事から、職種や部署の限定をせずにご応募いただけます。経験やスキル、適性や志向などを踏まえ、採用担当から配属先を提案させていただきます。

給与や手当、各種保険などの募集要項 [採用データ] とご応募から選考、入社までの流れをご案内。合わせて、マイナビキャリア採用 [経験者・第二新卒] でのよくある質問もご紹介いたします。